令和7年度税制改正法案(修正案)
その他4月の最新情報
令和7年度税制改正法案(修正案)
令和7年度税制改正法案および修正案が可決されました。年収の壁について政党協議を踏まえて令和6年12月に閣議決定された政府案が修正されております。 修正案の内容は、所得税の基礎控除の特例を創設し、当初改正案にさらに控除額を上乗せするものです。給与収入200万円相当以下(合計所得132万円以下)に係る上乗せは恒久的な措置となり、給与収入200万超に対する上乗せ措置については令和7年及び令和8年のみの措置となります。
〇給与所得者への影響額
|
給与額 |
合計所得 | 基礎控除 | 単身給与所得者1人あたり減税額(所得税) | |||
| 現行 |
大綱 |
修正案 |
修正案 | |||
| 上乗せ額 | ||||||
| 200万円以下 | 132万円以下 | 48万円 | 58万円 | 95万円 | +37万円 | 2.4万円 |
| 200万円越~475万円以下 | 132万円超~336万円以下 | 88万円 | +30万円 | 2.0万円 | ||
| 475万円越~665万円以下 | 336万円超~489万円以下 | 68万円 | +10万円 | 2.0~3.0万円 | ||
| 665万円越~850万円以下 | 489万円越~655万円以下 | 63万円 | +5万円 | 2.0~3.0万円 | ||
| 850万円超~2,545万円以下 | 665万円超~2,350万円以下 | 58万円 | ±0円 | 2.0~4.0万円 | ||
労務・税務のミニセミナー開催
令和7年4月18日(金)にミニセミナーを開催いたします。決算書を活用して経営状況を把握し、経営課題を見つける機会になれば幸いです。ご都合が合いましたら是非ご参加ください。
■ 日時:令和7年4月18日(金)13:30~15:30(参加費:無料)
■ 会場:信濃毎日新聞 茅野ビル1F(栁澤会計研修室)
■ 内容:第1部「決算書の基本と読み解きかた【貸借対照表・損益計算書編】」
第2部「改正 育児介護休業法対応」
次回以降のセミナーの予定は以下の通りとなっております。
| 開催日 | セミナー内容 | ||
| 令和7年6月19日(木) | 13:30~15:30 | 会計労務ミニセミナー | ・決算書の見方⓶・助成金 |
| 令和7年7月24日(木) | 15:00~15:30 | 会計労務ミニセミナー | ・調整中 |
| 令和7年9月18日(木) | 13:30~15:30 | 会計労務ミニセミナー | ・相続税・贈与税の重要ポイント・よくある労務トラブル |
| 令和7年11月14日(金) | 13:30~15:30 | 会計労務ミニセミナー | ・年末調整の制度と実務・就業規則のポイント |
※セミナーの日程、内容は変更になる場合がございます。
― 暦年課税制度と相続時精算課税制度-
贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。令和6年1月1日以降の贈与から、この課税方法に関する改正が行われ、どちらの制度を選択すべきかの判断がより複雑になっています。最適な制度は、贈与者と受贈者の関係や年間の贈与額などによって異なるため、それぞれ状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。今回は、推定相続人である子や孫への贈与の場合と推定相続人以外の孫等への贈与の場合での有利不利について紹介します。
1.暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較
| 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 | ||
| 贈与者 | 誰でも可 | 60歳以上の父母や祖父母 | |
| 受贈者 | 誰でも可 | 18歳以上の子や孫 | |
| 制度の選択 | 選択制なし | 贈与者ごとに選択 | |
| 基礎控除等 | 毎年110万円 | 毎年110万円の基礎控除 その他生涯で特別控除2,500万円 |
|
| 控除後の課税価格 | 贈与財産額ー基礎控除 | 贈与財産額ー基礎控除ー特別控除 | |
| 税率 | 累進課税 | 一律20% | |
| 申告の必要性 | 届出不要 | 届出必要 | |
| 相続時の 取扱い |
生前贈与の加算 | 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される | 毎年110万円超の額は過去にさかのぼって全て相続財産に加算される |
| 贈与税額控除 | 贈与税額は相続時の相続税から控除される(控除しきれない贈与税額の還付なし) | 贈与税額は相続時の相続税から控除される(控除しきれない贈与税額の還付あり) | |
2.推定相続人である子や孫への贈与
■相続までの期間が7年以内である場合
生前贈与の期間が7年以下の場合は、常に相続時精算課税制度が有利になります。これは、7年間の控除額が、相続時精算課税では最大770万円(110万円×7年)であるのに対して、暦年課税では最大100万円にとどまるためです。
■相続までの期間が7年超の場合
生前贈与の期間が7年よりも長い場合は、財産所有者の財産総額によって有利な課税制度が異なってきます。そのため、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを利用するかよく検討する必要があります。
3.推定相続人以外の孫等への贈与
推定相続人でない孫等には生前贈与加算の適用がなく、贈与税のみで課税関係が完了する暦年課税が有利になります。ただし、その推定相続人でない孫等が、贈与者の相続時に遺贈によって財産を取得する場合には、生前贈与加算の適用があるため、必ずしも暦年課税が有利とはいえなくなるため注意が必要です。
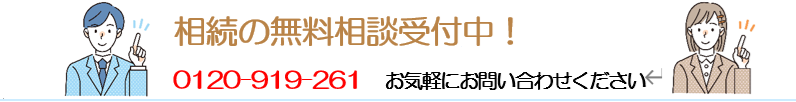
税金・会計 Q&A
税の制度をうまく使うと税金が安くなる?①(税額控除)
政府が促進したい特定の政策について、税制措置で税金を優遇する制度があります。ここでよく使われるものに「税額控除」と「特別償却」という制度があります。
1.税額控除とは?
「税額控除」とは、利益の額から算出された税額から特定の金額を差し引く制度です。
①利益(課税所得金額)×税率=税額
②税額-税額控除額=確定税額
|
計算式 ①課税所得金額500万円×税率25%=税額 125万円 |
2.税額控除の例
税額控除の制度には様々なものがありますので、代表的なものをご紹介します。
 ・設備投資をすると税額控除!(投資の活性化)
・設備投資をすると税額控除!(投資の活性化)
中小企業投資促進税制(取得価額×7%)
中小企業経営強化税制(取得価額×7%又は、取得価額×10%)
 ・試験研究をすると税額控除!(企業のイノベーション促進)
・試験研究をすると税額控除!(企業のイノベーション促進)
研究開発税制
・従業員給与等を増加すると税額控除!(個人所得の拡大)
税の制度をうまく使うと税金が安くなる?②(特別償却)
1.特別償却とは?
「特別償却」とは、通常の減価償却費とは別に前倒しで償却費を計上することで、資産の取得価額に一定割合を乗じた金額を特別償却費として計上し、利益を減額することができます。
2.特別償却の例
・中小企業投資促進税制:中小企業者等が機械等を取得した場合(取得価額×30%)
・中小企業経営強化税制:特定経営力向上設備等を取得した場合(取得価額の全額(即時償却))
※税額控除と特別償却が適用可能な税制は、どちらか一方を選択して適用します。
3.特別償却は、減価償却の前倒しです。
| ①通常の場合 | ②特別償却を適用した場合 |
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
| 取得価額 | 減価償却 | 減価償却 | |||||||
| 期末簿価 | 減価償却 | 特別償却 | |||||||
| 期末簿価 | 減価償却 | ||||||||
| 期末簿価 | 減価償却 | 期末簿価 | 減価償却 | ||||||
| 期末簿価 | 減価償却 | 期末簿価 | 減価償却 |
※減価償却及び特別償却は、最終的に「費用にできる金額=取得価額」となるため、特別償却を適用した場合、費用を前倒しで計上できることとなります。そのため税額控除と特別償却のどちらかを選択して適用する税制の場合は、長い目でみると減価償却とは別に税金を優遇してくれる「税額控除」がお得です。
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して省力化投資を支援する補助金で、「カタログ注文型」「一般型」の2つの類型があります。
 中小企業省力化投資補助金の交付額の一覧 (中小企業省力化投資補助金のPDF資料より引用)
中小企業省力化投資補助金の交付額の一覧 (中小企業省力化投資補助金のPDF資料より引用)
職員コラム ~家計調査って面白い~ 土橋 久美子
 2月に公表された令和6年分の総務省家計調査で、私の地元、静岡県浜松市が「1世帯当たりの餃子購入額2年連続1位」になりました。私自身、地元の人たちが特別にたくさん餃子を食べている印象はありませんが、餃子の持ち帰り専門店があり、一般家庭でも100個単位で買う、というのは他の地域にはあまりない特徴なのかもしれない、と思います。
2月に公表された令和6年分の総務省家計調査で、私の地元、静岡県浜松市が「1世帯当たりの餃子購入額2年連続1位」になりました。私自身、地元の人たちが特別にたくさん餃子を食べている印象はありませんが、餃子の持ち帰り専門店があり、一般家庭でも100個単位で買う、というのは他の地域にはあまりない特徴なのかもしれない、と思います。
さて、長野は、県庁所在地「長野市」の調査結果が公表されています。令和4年から令和6年の平均で購入額上位になったものは、「小麦粉」1位、「生そば・うどん」高松市に次いで2位、「しめじ」2位、「えのきたけ」2位、「りんご」2位、「ぶどう」2位、菓子類の中では「ようかん」が3位でした。
逆に、購入額が少ないものとしては肉類・魚介類があり、肉類全般では52都市の中で50位、魚介類全般は22位(うち、生鮮魚介44位、魚介の漬物4位、つくだ煮2位、缶詰3位)でした。
 この結果を見て、「小麦粉」は、おやきに使うのか?「ようかん」は、塩羊羹や栗羊羹の有名なお店が多いから購入額も多いのか?…と、美味しい長野の食べものを思い浮かべながら考えました。
この結果を見て、「小麦粉」は、おやきに使うのか?「ようかん」は、塩羊羹や栗羊羹の有名なお店が多いから購入額も多いのか?…と、美味しい長野の食べものを思い浮かべながら考えました。
この家計調査は、全国約9千世帯を対象に、家計の収支・支出、貯蓄・負債を毎月調査するもので、経済政策・社会政策の立案のための基礎資料となったり、民間企業のターゲット層分析に役立ったりするそうです。食べ物のことばかり書いてしまいましたが、世帯主の年齢層によって1か月の携帯代はどのくらい違うか?支払いはクレジットカードが多いのか、電子マネーが多いのか?など、意外で、細かな切り口の調査結x果が公表されていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。
出典 総務省統計局 家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング



